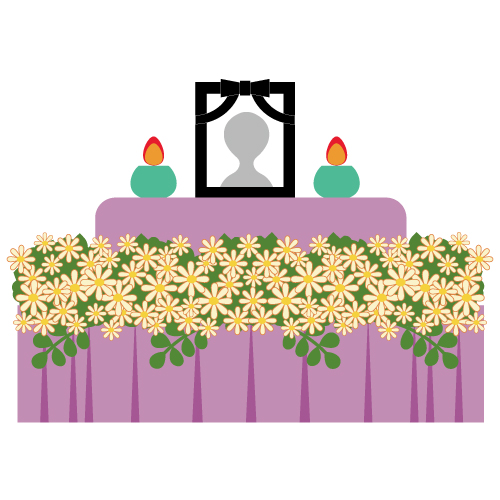突然の訃報は誰にでも起こり得ます。
動揺する中で「会社にはどう連絡すべきか」「忌引休暇は何日取れるのか」など、実務的な判断を素早く求められる場面が続きます。
本記事では葬式休み(忌引)の基本から、上司へのスマートな連絡手順、友人の葬儀や遠方・友引で日程が延びる場合の対処、さらには実際に使える例文集まで、初めてでも迷わないポイントを整理して解説します。
大切な人を見送る時間を守るために、必要な準備だけを確実に押さえましょう。
忌引休暇の基礎知識|就業規則で確認すべきポイント
最初に知っておきたいのは、忌引休暇は法律上の「義務的な休暇」ではなく、会社の就業規則で定められる制度だという点です。
多くの企業では、配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹など続柄に応じて日数が設定され、配偶者で最長、二親等で数日といった目安を定めています。
対象範囲や日数、賃金の扱い(有給か無給か)、起算日(通夜・葬儀当日・訃報日など)は会社により違うため、必ず就業規則と社内ポータルの運用ルールを確認しましょう。
証明書の提出は原則不要ですが、会社が定める場合は指示に従うのが基本です。
なお、対象外のケース(遠縁・旧友など)では、年次有給休暇や特別休暇、半休、時差出勤、在宅勤務など別の手段で調整するのが一般的です。
急なケースでも、まずは上司に状況共有し、就業規則上の扱いを一緒に確認する姿勢が信頼につながります。
迷ったら「忌引の対象かどうか不明だが、○日必要になりそう」という見立てを添えて相談するのがスムーズです。
関係(続柄)と日数の目安|「対象かどうか」の考え方
多くの企業での相場感として、配偶者:5〜10日前後、父母・子:3〜5日前後、祖父母・兄弟姉妹:2〜3日前後などとされています。
一方で、親等の解釈や同居・扶養の有無で日数が変わるなど、社内規程の差は大きいのが実情です。
近年は家族の形も多様化しており、事実婚や再婚家庭、パートナーの親族など個別事情が絡むこともあります。
この場合は、人事・上司へ早めに相談し、対象可否や日数の裁量の余地を確認しましょう。
対象外となる友人・旧知・恩師などの葬儀に参列したい場合は、年休または半休での対応が無難です。
葬儀・告別式は平日昼間が多いので、半休+時差出勤で調整する選択肢も有効です。
いずれにせよ、直前連絡は現場への負担が大きいため、わかった時点で即時連絡を入れるのが基本マナーです。
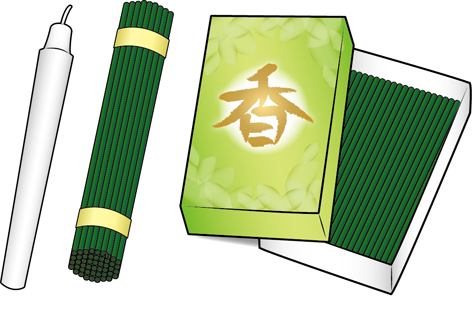
上司への連絡は「即時・要点完結」|誰に何をどう伝えるか
連絡の基本は直属の上司に電話(またはチャット・電話併用)で即時です。
深夜・早朝など緊急時はチャットで一次報告し、始業時間に電話で要点を補足すると丁寧です。
伝える内容は次の7点が目安です。
- 訃報の事実と続柄。
- 通夜・葬儀などの予定日、時間帯、確定or未定の別。
- 斎場名・所在地・電話(弔電送付に必要)。
- 必要見込み日数と起算の考え方(移動・友引考慮)。
- 担当業務の緊急度と引継ぎ先の提案。
- 連絡が取れる窓口(電話・メール・家族代行)。
- 社外対応の要否(自動返信・納期調整)。
「取り急ぎの一次連絡」→「詳細確定後の二次連絡」という二段構えにすると、上司も社内調整が進めやすくなります。
メールは証跡として便利ですが、最初の連絡は“声”でが鉄則です。
チェックリスト|弔電・香典・社内手続きでモレを防ぐ
会社は弔電・供花・香典の手配を慣例としている場合があります。
斎場情報を正確に伝えることが、先方への礼を欠かさないうえで最重要です。
社内手続きでは、勤怠申請区分(忌引・年休など)、起算日、添付要否、上長承認フローを確認します。
加えて、社外向けの自動返信や担当者代理の掲出など、外部コミュニケーションも即日整備しましょう。
- 斎場名・住所・電話・喪主名。
- 通夜・葬儀の日時(変更可能性があれば明記)。
- 香典・供花の取り扱い(辞退の有無)。
- 勤怠区分・起算日・申請方法。
- 社外自動返信の文面・期間。
- 代理担当の氏名・連絡先・対応範囲。

友人・知人の葬儀で休む場合|“忌引対象外”でも礼を尽くす
友人・知人・恩師の葬儀は、会社の忌引規程では対象外のことが多いです。
この場合は年休・半休・時差出勤を組み合わせ、「私用のため」+期間・業務影響を簡潔に伝えます。
プライバシー配慮が必要なら、続柄の開示は必須ではありません。
ただし、直前の欠勤連絡は控えるべく、予定が固まり次第すぐ報告するのがマナーです。
社外対応があるポジションなら、代理担当と自動返信の設定を先に済ませてから移動に入ると安心です。
近年はオンライン葬儀や配信の選択肢も増えています。
移動が難しい場合は上司に相談し、短時間の離席や在宅勤務での参加が可能かを検討しましょう。
遠方・友引・日程の空白に備える|移動日や追加休の考え方
遠方での葬儀では、移動と宿泊で日数がかさみます。
忌引日数に収まらない場合は、年休での上乗せが現実的です。
また、地域慣習で友引に葬儀を避けるため、通夜と葬儀の間に一日空くことがあります。
この「空白」を移動・手伝い・諸手続きに充てる旨を説明すれば、上司も必要性を理解しやすくなります。
復路は疲労が蓄積し、事故リスクも高まります。
翌日の午前半休や時差出勤を提案し、無理のない復帰計画を立てましょう。
あわせて、悪天候による交通遅延の可能性も織り込み、代替ルートと連絡網を準備しておくと安心です。
引継ぎと社内周知|当日でも最低限ここまで
急な欠勤でも、「誰が」「何を」「いつまでに」の三点を明確にしておけば業務の混乱は最小化できます。
同行資料・見積・進行表などのファイルは、共有ドライブのリンクを一つのメモにまとめ、代理担当と上司に送付します。
社外向けには自動返信で不在期間と代理窓口を明記し、緊急連絡先は社内のみに限定するのが安全です。
- 進行中タスクの一覧(案件名/現状/次アクション/期限)。
- 重要メールの転送・ピン留め。
- 打合せの任命替え・延期判断の基準。
- 社内チャットの固定メッセージ化。
休暇中のマナーと境界線|「連絡は取れるが対応は限定」
忌引は弔事に専念するための時間です。
原則として通常業務は行わない前提で、緊急時のみ着信確認という線引きを上司とすり合わせましょう。
SNSへの投稿は誤解や不快感を生む恐れがあるため控えめにし、写真の公開範囲にも配慮が必要です。
復帰後の「お悔やみ」への返答は、簡潔なお礼で十分です。
香典の扱いは地域差があります。
会社としての方針(辞退・連名・上限)を確認し、先方の意向に沿うことが最優先です。
弔電は読み上げられることもあるため、誤字や敬称を入念に確認しましょう。
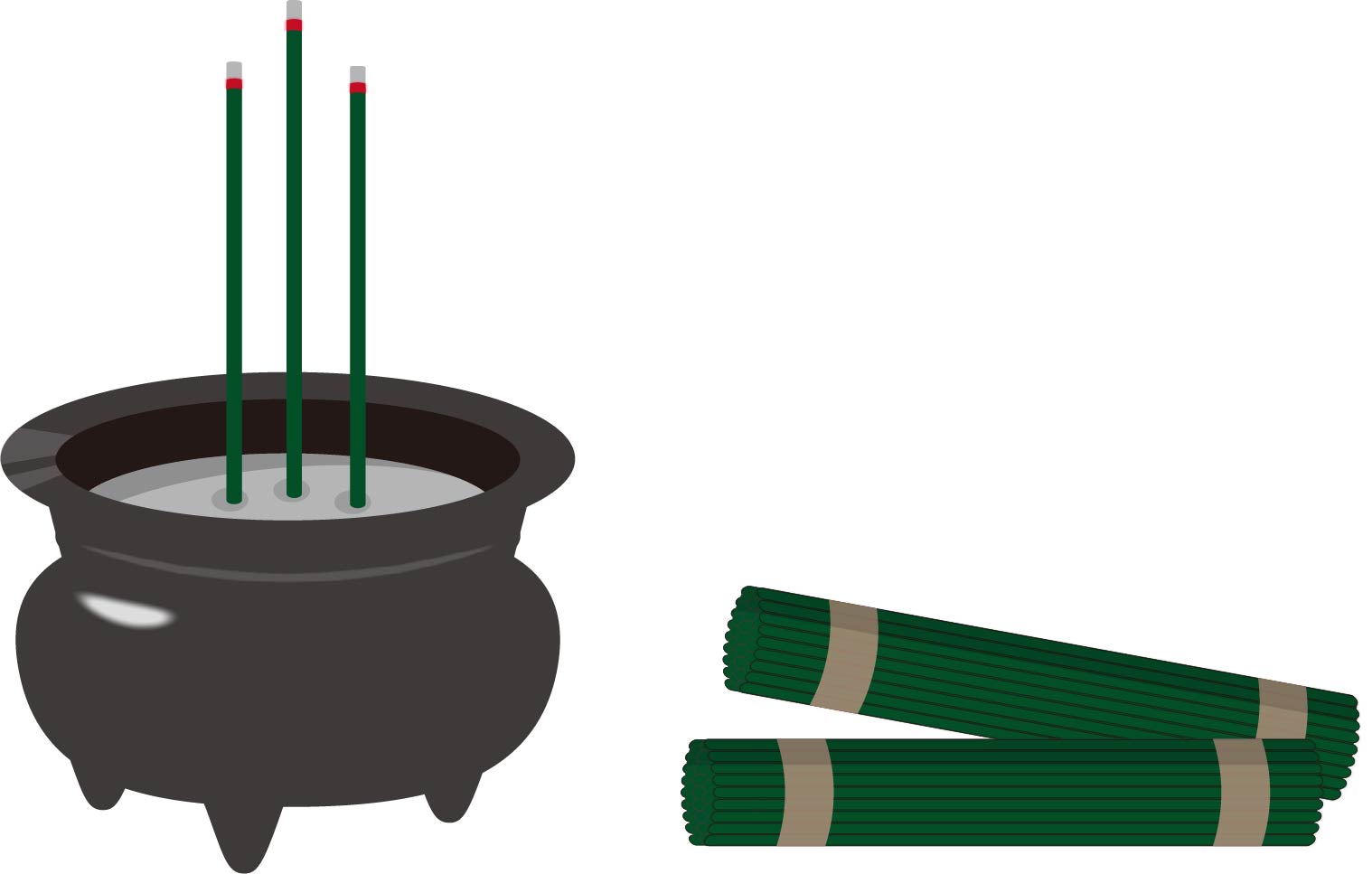
すぐ使える連絡テンプレ|電話・チャット・メールの例文
電話(一次連絡)
「お世話になっております。○○部の△△です。
本日、祖母が急逝し、通夜が○月○日、葬儀が○月○日を予定しています。
斎場は○○市の△△会館です。
忌引として○日、必要に応じて年休を上乗せしたく、取り急ぎご連絡しました。
詳細が確定し次第、再度ご報告します。
業務はメモにまとめ、代理は□□さんを第一候補として考えています。
ご指示いただけますでしょうか。」
チャット(補足)
「一次連絡の補足です。
斎場:△△会館(住所・電話)。
通夜:○/○(○)18:00、葬儀:○/○(○)11:00予定。
不在:○/○〜○/○。
代理:□□さん。
緊急時は携帯にお願いします。
弔電の宛先は喪主○○です。」
メール(確定版)
件名:忌引取得のご連絡(△△)
本文:お疲れ様です、△△です。
祖母の逝去に伴い、下記の通り忌引を取得いたします。
期間:○/○(○)〜○/○(○)<○日>。
通夜:○/○(○)18:00/葬儀:○/○(○)11:00。
斎場:△△会館(住所・電話)/喪主:○○。
代理:□□(連絡先)。
緊急時は携帯にて連絡可。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
よくある質問|証明書・対象外・服装・復帰後の流れ
Q:証明書は必要?
A:原則不要ですが、会社規程で求められる場合は指示に従うのが基本です。
火葬許可証のコピーや会葬礼状などで代替する企業もあります。
Q:対象外(友人など)で休みたい。
A:年休・半休・在宅などで調整します。
理由の詳細は伝えなくても構いませんが、早めの連絡と代理段取りは必須です。
Q:服装はどうする?
A:斎場へは喪服が基本です。
急な通夜で間に合わない場合は、地味な濃色スーツと白シャツ・黒ネクタイなどで対応します。
Q:復帰後は何をする?
A:勤怠の精算、経費(香典・供花)の精査、未了タスクの再開、関係者へのお礼を簡潔に。
体力・気力の回復も考え、過密な会議設定は避けるよう上司と調整を。
まとめ|「即連絡・就業規則・丁寧な引継ぎ」が三本柱
葬式休みの要点は、一刻も早い上司連絡、就業規則の確認、最低限の引継ぎ整備の三本柱です。
対象外の葬儀でも、年休や半休で礼節を尽くせます。
遠方や友引で日程が延びるときは、日数の根拠を添えて相談しましょう。
弔電・香典の手配は斎場情報の正確な共有が鍵です。
なによりも、大切な人を見送る時間を守ることを最優先に、社内外への配慮を短く、確実に重ねていきましょう。