食物アレルギーとは、特定の食べ物を摂取した際に体に不快な症状や危険な反応が起こる状態を指します。
特にアレルギー体質の人は、特定のタンパク質に対してIgE抗体を作りやすく、これが症状の引き金となります。
症状は通常、食物を摂取してからすぐ~2時間程度で現れる「即時型反応」が多いですが、まれに数時間後や翌日に出る場合もあります。
食物に含まれる毒性物質による反応は「食中毒」、体内で特定の成分をうまく消化できない場合は「食物不耐症」と区別されます。
この記事では、食物アレルギーの原因、症状、年齢ごとの特徴、重症時の対応、日常生活での予防策、具体的なケース対応まで、実践的に解説します。
食物アレルギーの原因とは
食物アレルギーの原因物質は「アレルゲン」と呼ばれます。
日本で特に多いのは卵、牛乳、小麦です。
その他、さばやいかなどの魚介類、バナナやキウイなどの果物、大豆、ピーナッツ、そばなどもよく知られています。
年齢によって原因となる食品の割合は変化します。乳幼児では卵や牛乳のアレルギーが多く、幼児期から学童期にかけては小麦アレルギーが増加します。
学齢期以降は、魚介類や果物、ナッツ類が原因になる割合が高くなる傾向があります。
統計によると、乳幼児の食物アレルギー患者の約60%が卵や牛乳に反応を示し、学童期以降は魚介類やナッツの反応が増加することが報告されています。
加工食品や調理方法によっても症状が変化することがあり、加熱済み卵は反応が出にくい場合があるなどの特徴もあります。
アレルゲン食品の理解は、予防や緊急時対応に直結します。

症状の種類と特徴
食物アレルギーの症状は多岐にわたります。
最も一般的なのは皮膚症状で、じんましんやかゆみ、赤み、顔や唇の腫れが現れます。
呼吸器症状では、咳、ゼイゼイした呼吸、呼吸困難が見られることがあります。
口や目の粘膜症状(口腫れ、目の充血や腫れ)や消化器症状(腹痛、吐き気、下痢)が同時に現れる場合もあります。
重症化すると、血圧低下や意識障害を伴うアナフィラキシーショックに至ることがあります。
具体例として、給食でピーナッツ混入により小学生がアナフィラキシーを起こし、救急搬送された事例があります。
同じ食品でも体調や摂取量、摂取方法によって症状が異なることがあるため、早期対応が重要です。
初期症状の観察と記録が、重症化予防につながります。
年齢とともに変わるアレルギーの経過
小児の食物アレルギーは、成長とともに軽快する可能性があります。
特に卵、牛乳、小麦は、入学前までに約8割の子どもが症状を起こさなくなるとされています。
しかし、すべての子どもが自然に治るわけではなく、個人差が大きいです。
一方、ピーナッツ、魚介類、果物、そば、種子類は耐性化しにくい傾向があります。
耐性化の進行は数年単位で異なるため、定期的な医師診察と経過観察が不可欠です。
家庭では、症状の記録やアレルゲン食品の管理、学校では給食対応マニュアルの整備が推奨されます。
医師の指導の下で、少量からの経口免疫療法を行うケースもあり、症状軽減に役立つことがあります。
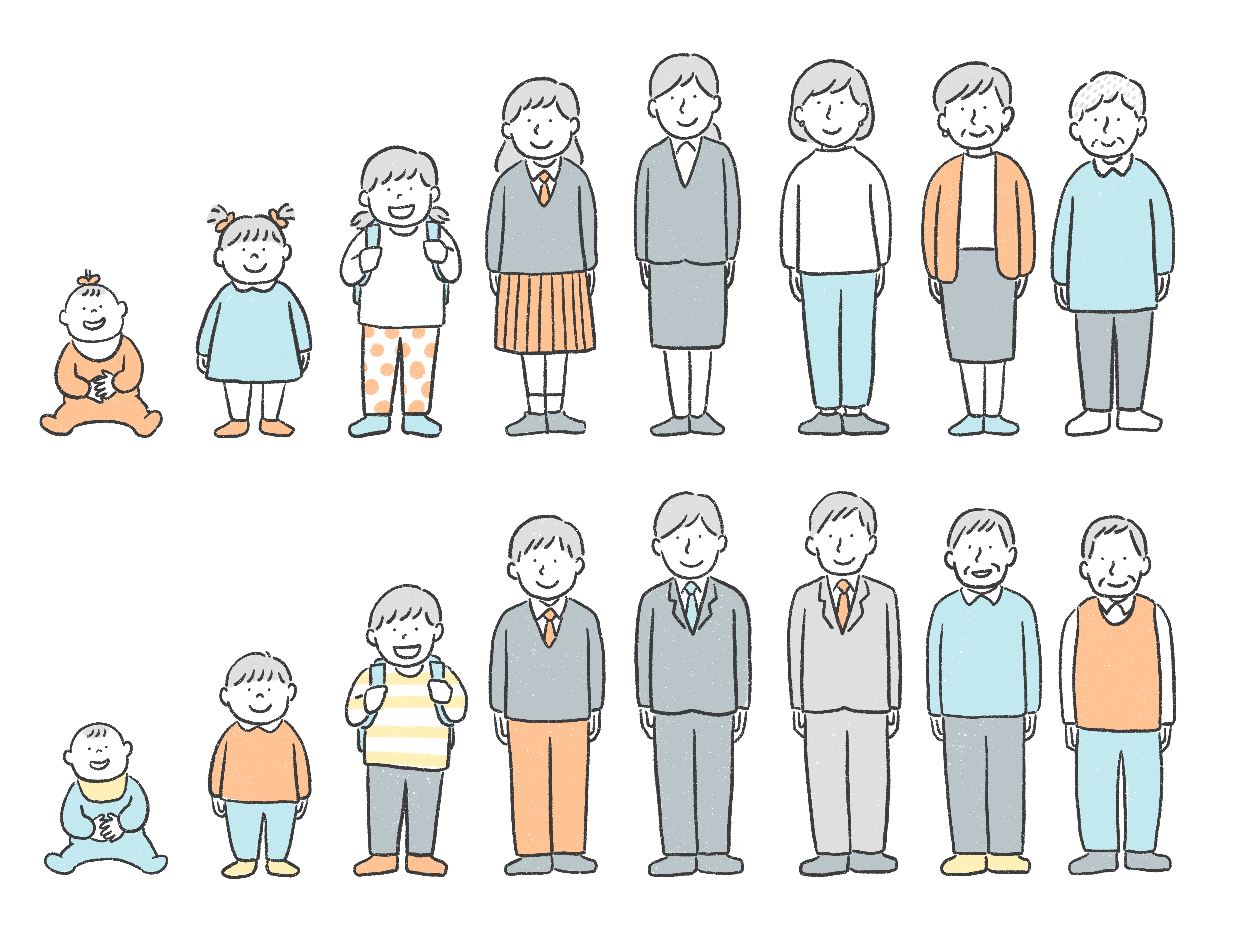
重症化のリスクと具体的対応
食物アレルギーは、軽度の皮膚症状だけでなく、重症化するリスクがあります。
特にアナフィラキシーショックは、迅速な対応がなければ命に関わります。
症状が急に現れた場合は、迷わず救急車を呼ぶことが必要です。
エピペンを処方されている場合は、使用方法を正しく理解し、緊急時に備えます。
学校や家庭では対応マニュアルを作成し、定期的な訓練が推奨されます。
軽度の症状でも、症状の進行を見逃さず、医療機関へ相談することが重要です。
症状の発生頻度や経過を記録しておくことで、医師の診断や今後の予防策に活かすことができます。
診断と検査の方法
診断は症状の観察と医師による検査で行われます。
血液検査では特定アレルゲンに対するIgE抗体量を測定します。
皮膚プリックテストでは、少量のアレルゲンを皮膚に接触させ、反応を見る方法です。
さらに、必要に応じ食物経口負荷試験を実施し、実際に食べた際の反応を観察します。
複数アレルゲンが関与する場合もあり、慎重な診断が重要です。
検査結果に基づいた食事管理や回避策の実践が、安全な生活に直結します。
医師との定期的な相談で、耐性化や治療の進行状況を把握することも推奨されます。

日常生活での予防と管理
食物アレルギーのある人は、日常生活での予防と管理が重要です。
まずはアレルゲンの特定と回避が基本です。
食事では食品表示確認、調理器具の共用を避けるなど、細心の注意が必要です。
学校や保育園では給食対応、緊急連絡体制、エピペン管理を徹底します。
旅行や外食時は、事前にアレルギー情報を伝え、対応可能か確認します。
また、家族や周囲への情報共有も不可欠です。
具体的には、旅行時にアレルギー対応メニューのあるレストランを選ぶ、持参食を用意するなどの工夫が有効です。
こうした管理と情報共有が、食物アレルギー事故防止の最大の対策になります。
ケーススタディ:実践的対応例
【学校給食での誤食】
小学生が給食でピーナッツ入りパンを誤って摂取し、軽度のじんましんが出た場合。
対応策:教師が即座に医務室へ連絡、エピペンを使用、救急搬送。
事後対応:学校給食の管理マニュアルを見直し、アレルギー児対応の再教育を実施。
【外食時の対応】
アレルギーがある成人がレストランで魚介類料理を注文する場合。
対応策:事前に店員にアレルギー情報を伝える、可能であれば事前メニュー確認、万一に備えエピペンを携帯。
このように日常生活の具体的なシーンごとに行動指針を準備することで、事故リスクを大幅に減らせます。
まとめ
食物アレルギーは、卵、牛乳、小麦、魚介類、果物、ナッツ類など多くの食品で発症の可能性があります。
症状は皮膚、呼吸器、粘膜、消化器にわたり、重症化すると命に関わることもあります。
小児では成長とともに症状が軽快することもありますが、耐性化しにくいアレルゲンも存在します。
日常生活ではアレルゲン回避、症状の早期発見、緊急時対応、情報共有が重要です。
医師の診断、血液検査、皮膚テスト、家庭・学校での管理、外食・旅行時の対応策を組み合わせ、安全な生活を守りましょう。
具体的なケースを想定し、対応マニュアルを作成しておくことで、万が一の際も落ち着いて行動できます。


